-
about us
会社概要
-
to BUSINESS
法人のお客様
-
to CUSTOMER
個人のお客様
-
RECRUIT
採用情報
-

-


ふるさとに
芸術・文化・伝統・風土を育む
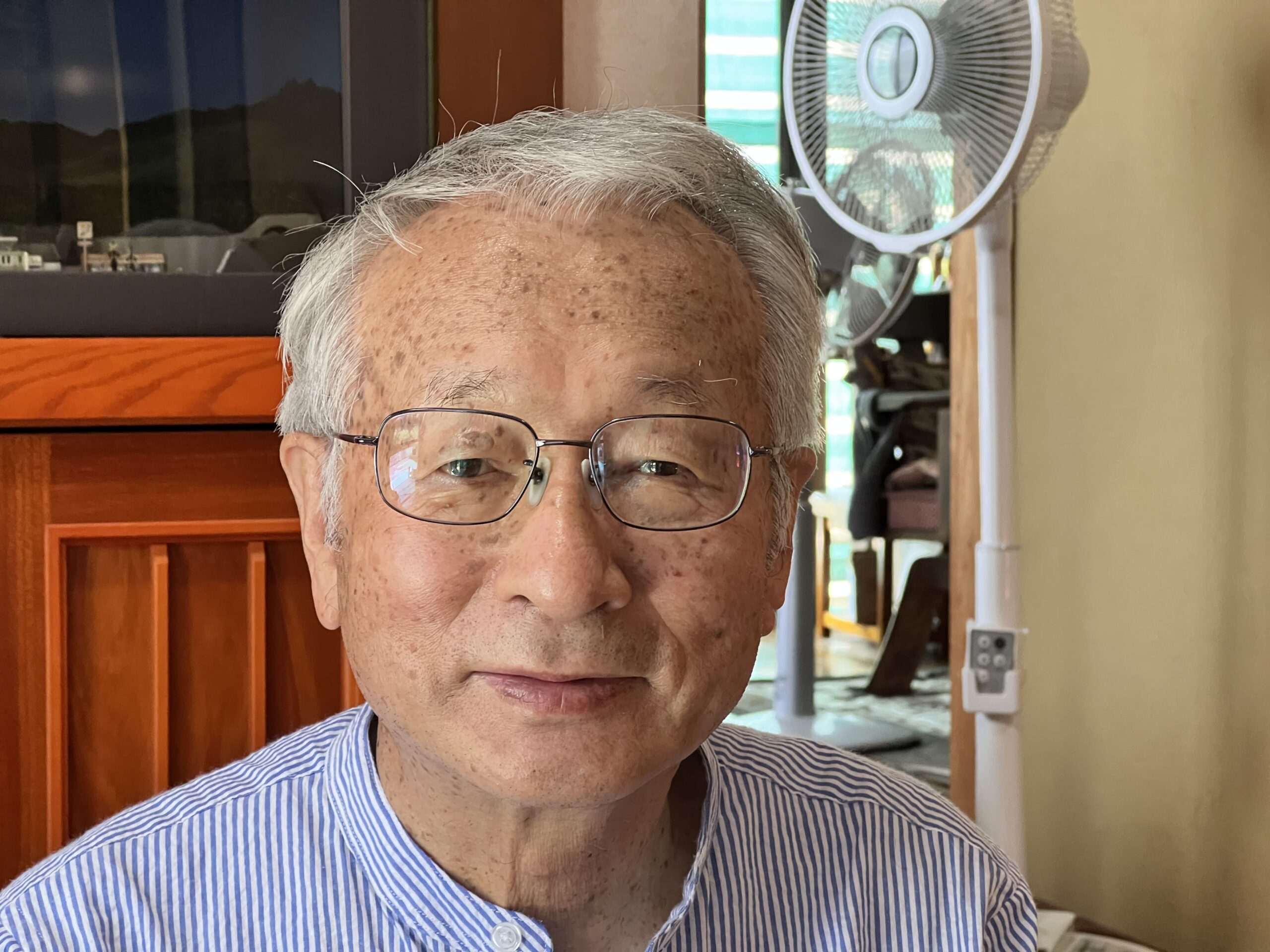
今回は近江八幡市千僧供町にお住いの木工芸家、小梶宗二さんをご紹介します。
70歳まで高等学校で教鞭をとられていた小梶さん。「新しい事を始める丁度良い機会」と竹細工教室のパンフレットにあった竹灯籠に目が留まりました。早速、妹背の里を活動拠点にしている竹灯籠の愛好グループ主催の教室に申し込みをされ、竹灯籠づくりに挑戦です。彫刻細工がしやすい様に50cm程にカットされ、肉厚も薄く加工された竹筒とカーボン紙、カッターナイフと希望する絵柄の型紙を渡されます。竹灯籠教室の1クールは1回2時間の教室を、2週間毎に4回開かれます。小梶さんはまず、灯篭づくりのポイントと工程を学ぶために、2時間の竹灯籠教室の大半を製作している生徒さんの取組みの観察と、疑問点の質疑に費やされます。「材料づくりから絵柄の加工方法まで、制作に取掛る準備工程や必要な道具など解らない事ばかりです。だから皆さんの制作姿勢を見せてもらいたかったんです。デザインに使う絵柄の選定も難しく、版権が必要か不要かなど未だに解らない事もあるんです」と話されます。初めての事に挑戦する際、不安を取除く問題解決は重要ですよね。安心して挑戦できる事前情報の提供ってなかなかないですからね。竹灯籠づくりの要諦を把握された小梶さんは、竹灯籠教室を1クール終了後、竹の伐採から竹灯籠の細工が出来る竹筒作りまで、自分ひとりで完結出来る様にと新たな挑戦に取組まれます。秋に成長した材料を確保するために、奥様と二人で知人の竹林に現在も行かれています。「直径20cmほどの竹を選び、切倒した1本から長さ2mくらいの長さに切りそろえて、自動車に積込み家まで運びます。足元も不安定で良くないし、80歳を超えた今ではとても重労働なんです。勿論、切倒した竹は持ち帰り、自宅の塀や外回り材料として使うんですよ。」と言われます。山から取ってきた竹はしばらく乾燥させ、その後、節と節の間をノコギリで切断、竹筒のピースにしてナタで薄く切取り、楕円形に加工されます。彫刻細工しやすい様にと同時に、彫刻を施す面を広くして竹灯籠がより映えるようにするためだそうです。
そしていよいよ彫刻細工の工程です。原画をカーボン紙で竹筒に写し、一ヶ月間かけて彫刻細工を施されます。写真でお判りの様に、とても緻密で繊細ですから作業は大変。「今回の鬼滅刃は原画に惚れ込んで挑戦しました。細かくて危なそうな場所は後に回し、丈夫で安心できる場所から彫ります。気分転換も兼ねて同時進行で3~4本彫るんで、一つに掛ける時間は15分ほど。それを繰返して仕上げては、作業途中に中から光を当てて仕上がりをチェックしています。時には仕上げ途中で彫刻が欠けることもありますが、それは全て私のこだわりで捨てています」と話されます。凄い作家魂ですね。竹灯籠は明かりが灯って初めて完成だと、小梶さんは言われます。足つきの木製台を制作し、LEDのナツメ球のソケット、スイッチ、そしてプラグの配線をご自分で作業をされ、ようやく竹灯篭として完成です。細やかな細工が今にも飛び出しそうで、綺麗に彫刻細工を灯しています。
精魂込めて造られた作品は、地域の公民館活動での展示などで、少しでも多くの皆さんに見て欲しいと展示参画されています。お伺いした日もたくさんの作品が並んでいたので、私に見せるためだと思ったのですが、なんと室内干しをされているのだとか。「年に数回室内干しで風を通さないと、虫がついたりカビるんです」とのこと。室内干しの時にも知人やご近所さんが訪れることもあり、鬼滅の刃の竹灯篭に子供たちが歓声を上げるようです。益々のご活躍をお祈りします。



